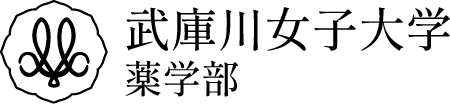教員・研究室
生物系研究室
環境衛生学研究室
教員
-
 教授山下 沢
教授山下 沢- 専門分野 /
- 衛生化学、生物物理化学
薬学部での勉強は非常に幅広い知識が求められますが、その分、色んな可能性が広がります。また、研究室で行う研究は、自分の将来に繋がる非常に有意義なものになるでしょう。 自分が学生時代に感じた、薬学の研究に対する『難しい』けど『面白い』という気持ちを学生さんに少しでも感じてもらえるように頑張りますので、素朴な疑問でも気軽に質問してください。 勉強はもちろんですが、勉強以外のことについても、大学生のうちに経験することは一生の宝になります。仲間と楽しく、そして充実した学生生活を送ってください。
-
専門分野 衛生化学、生物物理化学 最終学歴 熊本大学大学院薬学研究科博士後期課程 学位 博士(薬学) 所属学会 日本薬学会、日本生物物理学会、日本蛋白質科学会、SBIC 出身高校 西南学院高等学校 研究テーマ 化学物質の働きに関する酵素学的研究 担当科目 化学物質の生体への影響、衛生と社会、生活環境と健康、など その他 2004-2006:熊本大学大学院医学薬学研究部 産学官連携研究員
2006-2007:Postdoctoral Fellow, Ecole Polytechnique, France
2007-2008:Marie-Curie Fellow, Ecole Polytechnique, France
2008-2013:大阪大学大学院薬学研究科 助教
2013-2014:大阪大学未来戦略機構 特任准教授
2014-:現職
-
 助手堀江 美都里
助手堀江 美都里- 専門分野 /
- 衛生化学
薬学部で学ぶ知識は幅広く、その量は膨大です。しかし学びを進めていくと、薬学が「体・生活・社会」という身近なものに寄り添う学問であることが分かります。これらを理論立てて身に着けていくことは、薬学に関わる仕事に就くことだけでなく、生涯を通じて自らを支える大きな力になっていくと感じています。頑張っているみなさんのお役に少しでも立てるよう、お手伝いさせてください。
-
専門分野 衛生化学 最終学歴 武庫川女子大学薬学部薬学科卒業 学位 学士(薬学) 出身高校 福岡県立博多青松高等学校 研究テーマ 環境要因が生体機能に及ぼす影響に関する研究
研究室

病気になって薬で治療するのは二次予防です。でも、病気にならないための対策がはるかに大切な一次予防。食品や空気や水の中の、化学物質の人体への有益性と有害性の機構を解明し、健康を確保する衛生化学は智恵と工夫の一次予防の薬学です。現在、私達の研究室では、微量機器分析のほか、動物レベル、細胞レベルそして遺伝子レベルで化学物質の特性について次の3テーマに取り組んでいます。
健康確保のために食品への期待が高まるとともに、食品添加物に対しても大きな関心が持たれるようになってきました。私達は、食品添加物の微量分析法の開発を進めると同時に、培養細胞を用いて食品添加物の影響を調べています。最近の研究成果から、保存料の一種であるソルビン酸が、ガン化マスト細胞の増殖を抑制することが明らかとなりました。今後も食品添加物による生体影響のメカニズムを研究することにより、食の安全に貢献していきたいと考えています。
近年、アレルギー、アトピー性皮膚炎、化学物質過敏症およびシックハウス症候群などの健康被害が社会問題となっています。これらの病気は、食環境、化学環境、ストレス環境などに相互影響されることが知られています。さらに、アレルギーは免疫系だけでなく、神経系、内分泌系、代謝系と深く関係しているとされていますが、未だ不明確な部分も多く残されています。私達は、マウスなどの動物実験系を用いて、食品中のアレルギー原因物質の検出、シックハウス症候群の原因となる化学物質やストレス環境が免疫系や内分泌系に与える影響などの研究を行っています。これらの研究を通して、アレルギーまたは化学物質過敏症の人がどのように種々の環境要因と向き合ったらいいのか、さらにアレルギー体質の人の医薬品適正使用のための基礎研究などの社会的ニーズに貢献します。
核内受容体は、性ホルモンのエストロゲンやアンドロゲン、副腎皮質ホルモン、甲状腺ホルモン、脂溶性ビタミンのビタミンAやDなど、多くの生理活性物質の受容体として生命現象の様々な局面で重要な役割を果たしています。核内受容体に結合する分子は、すべて低分子で脂溶性の化合物であることから、これをターゲットとした多くの薬剤が開発され、抗癌剤や糖尿病治療薬として臨床的にも利用されています。同時に、核内受容体は環境汚染化学物質の標的にもなり、内分泌かく乱作用などの毒性発現にも関与することが知られるようになってきました。私達のグループでは、核内受容体を介する化学物質の作用発現を研究することにより、人類を含めた地球上生物の健康に貢献することを目標に研究を進めています。