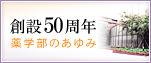共用試験OSCEを担当する

岡村 昇
OSCE企画運営委員長
薬学共用試験OSCEについて
薬剤師を目指す薬学部(6年制)の学生は、平成18年度入学生から、6年制となりました。問題解決能力を備えた実践的薬剤師の教育には6年間の学習期間が必要と考えられたからです。その大きな柱として5年次に病院と薬局に11週間ずつ参加型の実務実習を受けることとなりました。実際に病院や薬局に行って指導者の監督のもとで薬剤師の業務を行う実習によって、実践的な力を養うことが目的です。しかし、薬剤師と同じ業務を行うためには、それなりの能力が必要とされます。そのことを評価する試験が共用試験で、4年次の最後に全国の薬系大学で同じように実施されています。共用試験は、知識を評価するCBT(Computer-based Testing)と技能・態度を評価するOSCE(Objective Structured Clinical Examination;客観的臨床能力試験)から成ります。自動車の仮免許試験でも筆記試験と実技試験がありますが、OSCEは実技試験に当たります。
では、OSCEとは具体的にどんな試験でしょうか。簡単に言えば、基本的な薬剤師の業務を行うことができるかどうかを評価する試験です。薬剤師の業務は多岐にわたっています。そのうち、一部を切り取った課題が与えられます。例えば、「処方せん通りに錠剤やカプセル剤を調剤することができるか」とか「患者さん相手に薬の使い方を説明できるか」といった課題です。どの課題も1、2分で課題を読み、5分間で実技を行います。受験者1人に対して、2人の評価者が評価します。チェック項目が正確に実施されたか、病院・薬局で実習に行っても大丈夫か、といった観点から評価していきます。全部で6種類の課題が出題され、全てに合格しなければ病院・薬局実習に行くことはできませんが、4年次に行う事前学習をきちんと受けて、練習さえしておけばほとんどの人が合格することができます。また、事前学習の内容をしっかりと身に付けておけば、5年次の病院・薬局実習がより有意義なものになるでしょう。
これまでに、平成21、22年度に2回のOSCEを実施しました。受験者は非常に緊張して取り組んでいましたが、日頃の成果を十分に発揮してくれ、ほとんどの人が本試験で合格しました。わずかな人が一部の課題で不合格となりましたが、再試験で全員合格することができました
| 旧課程の学生を対象としたトライアルの様子 | ||
 |
 |